| ベッドからだらりと伸びた自分の腕を見た。無気力だ。 目に見えるすべてがぼやけていたので自分の腕かどうかも定かでなかったけれど、なんとか手探りでレンズ越しの視界を取り戻す。眩暈と頭痛と酒気帯びた口内が気持ち悪い。 散らかった部屋は一度たりともきれいだった試しがなくて、それでもどこか居心地がよかった。のはきっと、この部屋の住人である彼女が少しでも自分を許容してくれているという実感があったからだろう。 カーテンがそよいで、白いレース模様がふわりと揺れる。あまりに穏やかな光景であったから、頭の隅を何かがちらつくようによぎった。夢の中の母親であった。 僕は母さんというものを知らない。もう片方の腕の中で眠っている彼女とは、真逆の、偶像。光に照らされながら、焦点が定まっていくのと同じくらいの速度で、ふいにそれは瞬きを始めた。朝の静けさと共に彼女は、気だるそうに欠伸をしながら猫のように丸めていた上半身を起こしたのだった。 「おはよう」 そっけなく発したはずのそれは自分が思うよりも擦れていて、目をこすりながら彼女は、ん、とかああとか曖昧な返答をするのだ。これが日常だ。 (日常か) 思い返し、立ち上がった彼女の足首から、頭のてっぺんまでをゆっくりと目で犯した。朝からどうかしてるな。 いつの間にか彼女の裸を見慣れてしまった。なだらかに降下する腰の曲線に目を伏せて、肌のやわらかさ、染まる頬、その温度を思い返す。 遠くから電気のじりじり焼ける音と、それを閉じ込める音とがあって、アルコールの貯蔵庫の中からミネラルウォーターを片手に彼女が戻ってくるのがわかる。 裸足の足音、フローリングとの接着面、僕らの重心。 水を含んで濡れた唇を、乱暴に拭っているのを見た瞬間、胸の内のざわつきは慌しく波打って、痺れていたはずの右腕が伸びていく。渡されるあろうペットボトルが重力に逆らうことなく落下した。 鎖骨の窪み、首筋に唇を寄せて、肩に顔を埋めた。彼女の皮膚の、やさしい匂い。 ありったけの自分を、吹き飛ばすように笑ってくれれば。 たったそれだけでよかったんだ。 「どうした、」 寝起きの低い声が水のように落ちていく。それはじんわりと僕の心に染み渡り、いずれ溶けてなくなっていく。 (言葉はなくとも) 思いも気持ちも、届いてしまったら消えてしまう気がして、だから僕は彼女に暴かれたかった。 「抱きしめさせてよ」 いつかこの関係にも終わりがくるのだろうか。 僕たちは男と女で、そもそも、はじめから人間だった。 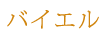 |