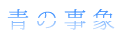| 賛美歌が聞こえる。 懐かしい記憶の奥底から流れ出す、人の声の織り成す音はどこまでも美しさを保ったまま、父の残像とともにフェードアウトしていく。 暗闇の中で光る十字。そろりと眼球を動かすけれど、その対象は一度だって変わらない。目の端に映るのは毛布に包まる兄の姿で、夜更けに盗み見るような行為を繰り返すたび僕は少しだけ安堵する。 平穏だ。このときばかりは愛しさと罪悪感とが胸の奥でじわりと広がっていく。 こんな日常が、毎日が、続くわけがない。一歩進むたびにまたひとつ兄との距離が遠ざかる。 そろりとベッドを抜け出すと、古びた床が軋んで悲鳴ともつかない音を立てた。 いつの間にか規則正しい寝息がすぐそばにあって、なのに兄さんは僕を見ることをしない。近づいていても、こんなに遠い。 (死人のように枕元に立ってやろうか) 息をするのもやめて、眼鏡を外したままのぼやけた視界の中でゆっくりと首を項垂れて、自身の手のひらを見やる。欲望の手だ。暗がりに浮かぶ不気味な白さの中に、兄には到底及ばないはずの、何もかもを手に入れたはずだった。 いつかの花を手折ったそれと、それを救い生かした兄と、僕はどこから違っていたのだろうか。生まれついたときから僕の心臓はこんなにもつめたく冷え切っていて、今ですら口元に微笑を称えているのに。 (僕を汚してくれ、兄さん) 頼りなく震える指先は、恐れながらも確実に彼の喉元に伸びていく。彼だけが本当を知っていて、自身のすべては嘘でできている。どうして僕たちは世界で二人きり、そうして一人きり。 悲しくなんてなかった。ただただ向こう岸で笑う兄のところへ行きたかった。 幼さの滲む声をなくして、いつの間にか追い抜いていた背丈も、本当は全部兄さんのものなんだ。 (本当はひとつになって溶けてしまいたかったよ) 眠っている兄の、閉じられた瞳の美しさを思う。目の前に広がるのはあたたかな鼓動とやさしい目をして笑う彼の、青く青く透き通っていく、あるがままの、心。 (このままあの青に沈んでいけるなら、僕はそれでもよかった) 美しさに憧れた、硝煙の匂いが染み付いている、乾いた指先を彼の首に翳して。 |